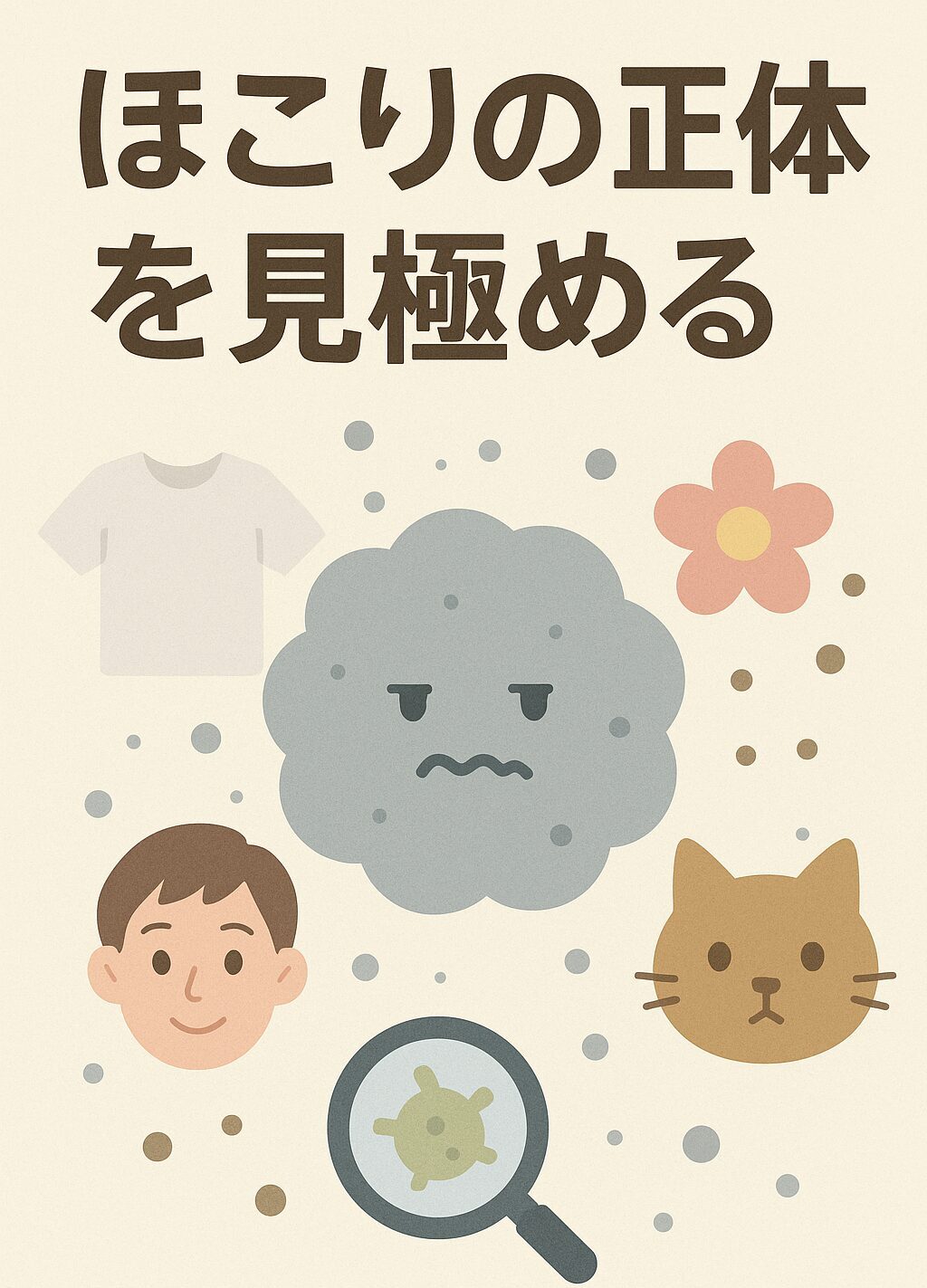訪問看護を行うなかで、利用者様のお宅に入った瞬間に、「なんとなく空気が重い」「鼻がムズムズする」「光の加減で空中に白いものが舞っている」と感じたことはありませんか?
その原因の一つが、「ほこり」です。
ほこりは単なる不快な存在にとどまらず、高齢者や持病を抱える方にとっては健康リスクや精神的不快感の原因になりうるものです。
この記事では、訪問看護スタッフが知っておくべき「ほこり」の基礎知識と、現場での観察力、さらには実際にできるアドバイスまで、包括的にお届けします。
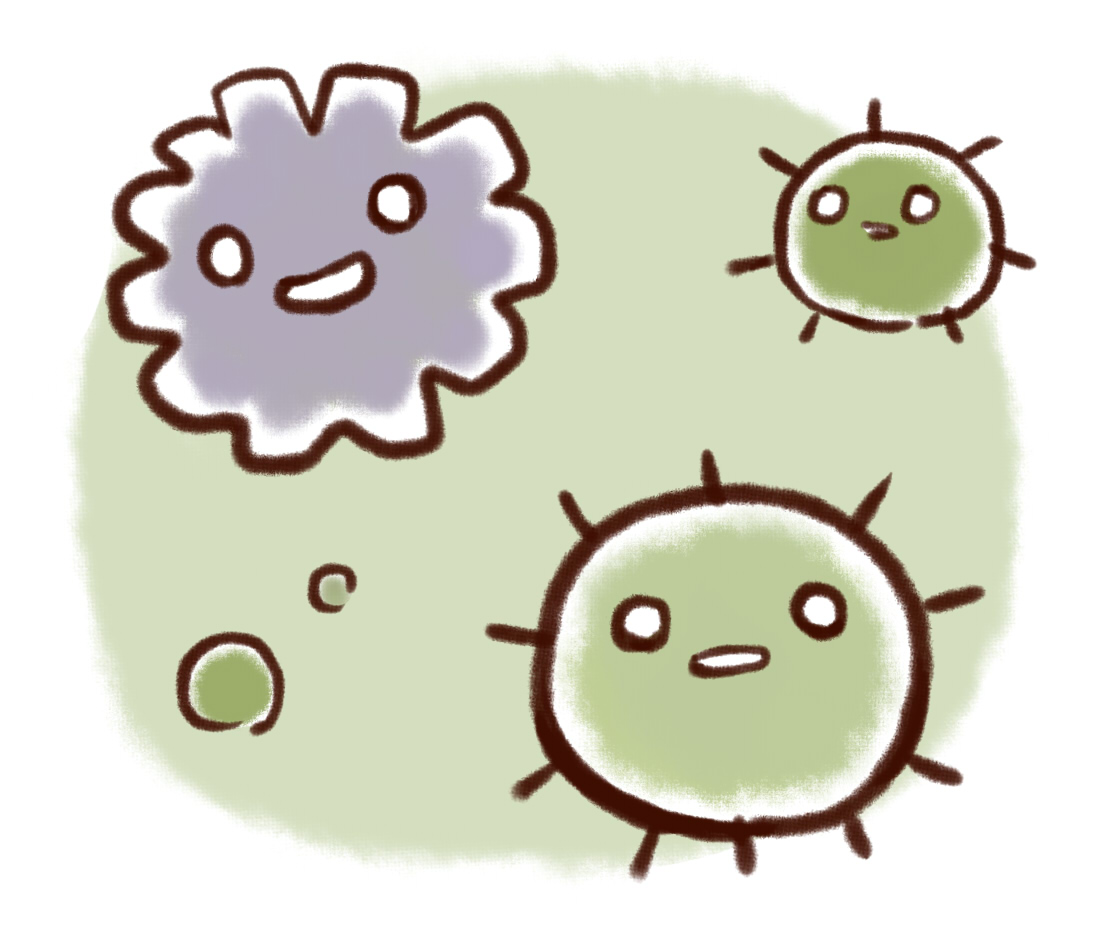
【1】ほこりとは? ─ その正体と主な成分
ほこりは、以下のような身の回りの物質が混ざり合ってできた粒子です:
| 成分 | 内容 |
|---|---|
| 衣類や布製品の繊維くず | カーテン、シーツ、衣類から発生 |
| 人体由来のもの | フケ、皮脂、髪の毛など |
| 外から入る粒子 | 花粉、土埃、黄砂など |
| ペット由来の物質 | 毛や皮膚片、フンの微粒子 |
| カビの胞子・ダニの死骸やフン | アレルゲンとなる物質が多い |
これらは見えにくいサイズ(直径1mm未満)のため、知らぬ間に積もり、吸い込まれ、体内に取り込まれることもあるのです。
【2】なぜ、利用者様宅ではほこりが溜まりやすいのか?
訪問看護を行っていると、比較的どの家庭でも共通して見られる“ほこりの傾向”があります。特に高齢者世帯や体力や動作能力に制限のある方のお宅では、以下のような要因でほこりが溜まりやすくなっています。
▸ 掃除頻度の低下
- 関節痛や疲労感により、掃除機や雑巾がけが負担になる
- 生活することで精一杯になり、掃除にかける時間や体力がない。
- 「今日はまあいいか」と日々後回しにされやすい
- 清潔に対する認識の歪み
▸ 換気不足
- 季節や防犯上の理由から窓を閉め切りがち
- 空気の入れ替えができず、ほこりが舞ったまま室内を循環
▸ 収納と物量のバランス
- 昔の物を捨てずに残しておく傾向があり、物が多い
- 思い出の品を保管しておきたくなる
- 家具の上や隙間に掃除が行き届きにくくなる
▸ ペットを飼っているケース
- 室内で動物を飼っていると、抜け毛やフケが増える
- 敏感な方にはアレルゲンになることも
【3】ほこりが身体・精神に与える影響とは?
ほこりは単なる「見た目の問題」ではありません。
実は、慢性的な体調不良や精神的なストレスの要因にもなり得るのです。
身体面への影響
| 症状・状態 | 解説 |
|---|---|
| 呼吸器疾患の悪化 | 喘息・慢性呼吸器疾患・慢性気管支炎の方は、微細なほこりが悪化因子に |
| アレルギー反応 | ダニのフン・死骸やカビ胞子により、くしゃみ・目のかゆみ・鼻水 皮膚のかゆみなどトラブルがでる。 |
| 感染リスクの増加 | 免疫力が低下している方は、カビや雑菌によって体調を崩すことも |

精神面への影響
- 空間の乱れ=心の乱れとも言われるように、視覚的にほこりが目立つと、不快感・落ち着かなさにつながる
- 「掃除ができていない自分」への自己嫌悪や、「片付けなきゃ」というストレスを抱える方も
【4】訪問スタッフとしてできる「気づき」と「助言」
では、私たち訪問看護のスタッフができることとは何でしょうか?
▸ まずは“気づく”こと
訪問時に「ほこり」が溜まりやすい箇所をチェックする視点を持ちましょう。
| チェックポイント | 見落としがちな例 |
|---|---|
| 家具の上や隙間 | タンスの上、ベッド下、TV裏 |
| エアコンの吸入口 | フィルターがほこりで目詰まりしていないか |
| カーテンや布団 | 洗濯頻度や日干し状況 |
| 換気状況 | 換気扇や窓の開閉習慣 |
▸ 優しい声かけで“気づき”を共有
「最近くしゃみが出やすいっておっしゃっていましたが、もしかしたら空気中のほこりが原因かもしれませんね」
といったように、体調や室内環境のつながりに気づかせる声かけが大切です。
▸ 無理のない対策を提案する
- 「ベッド下だけでも1ヶ月に1回拭き掃除しましょうか」
- 「エアコンのフィルターは1シーズンごとに確認してみましょう」
- 「物が多くて大変なときは、片付け支援のサービスもありますよ」
- 訪問介護などの介護保険サービスの導入をケアマネジャーさんに提案する
- 介護保険サービスでない、家事サービスの提案
訪問看護は医療行為だけでなく、生活支援も含めたトータルなサポートが期待されています。
【5】どうすれば改善できる? 具体的な「ほこり対策」
基本の掃除習慣
| 対策 | ポイント |
|---|---|
| こまめな拭き掃除 | 乾いた布ではなく、軽く湿らせて拭くと舞い上がりにくい |
| フィルター掃除 | エアコン、空気清浄機、加湿器のフィルターを定期的に洗浄 |
| 不用品の処分 | 物が減ると掃除がしやすくなり、ほこりの発生源も減少 |
換気の工夫
- 1日1〜2回、数分でも良いので窓を開ける
- 換気扇やサーキュレーターで空気を流す導線を作る
布製品の管理
- カーテン、布団、クッションなどは季節ごとに洗濯・交換
- 静電気防止スプレーを使うと、ほこりの付着を防げることも
【6】どうしても難しい場合は、プロの力も選択肢に
高齢の利用者様や障がいをお持ちの方にとって、「自分でやる」には限界があることも事実です。
そこで、必要に応じてプロの清掃サービスの利用を提案することも検討してみましょう。例えば、以下のようなサービスです:
[お掃除マスターの詳細を見る【お掃除マスター】]
プロによる定期清掃を導入することで、呼吸器疾患の悪化防止やQOL向上につながるケースも多く見られます。

【7】まとめ:ほこりに目を向けることは、ケアの質を高める第一歩
訪問看護において、身体の変化や病状の管理と同じくらい大切なのが、生活環境の観察です。
「ほこり」が目立つという事実に気づき、その背景と影響を理解することは、利用者様の安全・安心・快適な生活を守る第一歩となります。
ぜひ、今後の訪問の際には“空気の質”にも注目し、利用者様と一緒に住環境を整える取り組みを進めていきましょう。