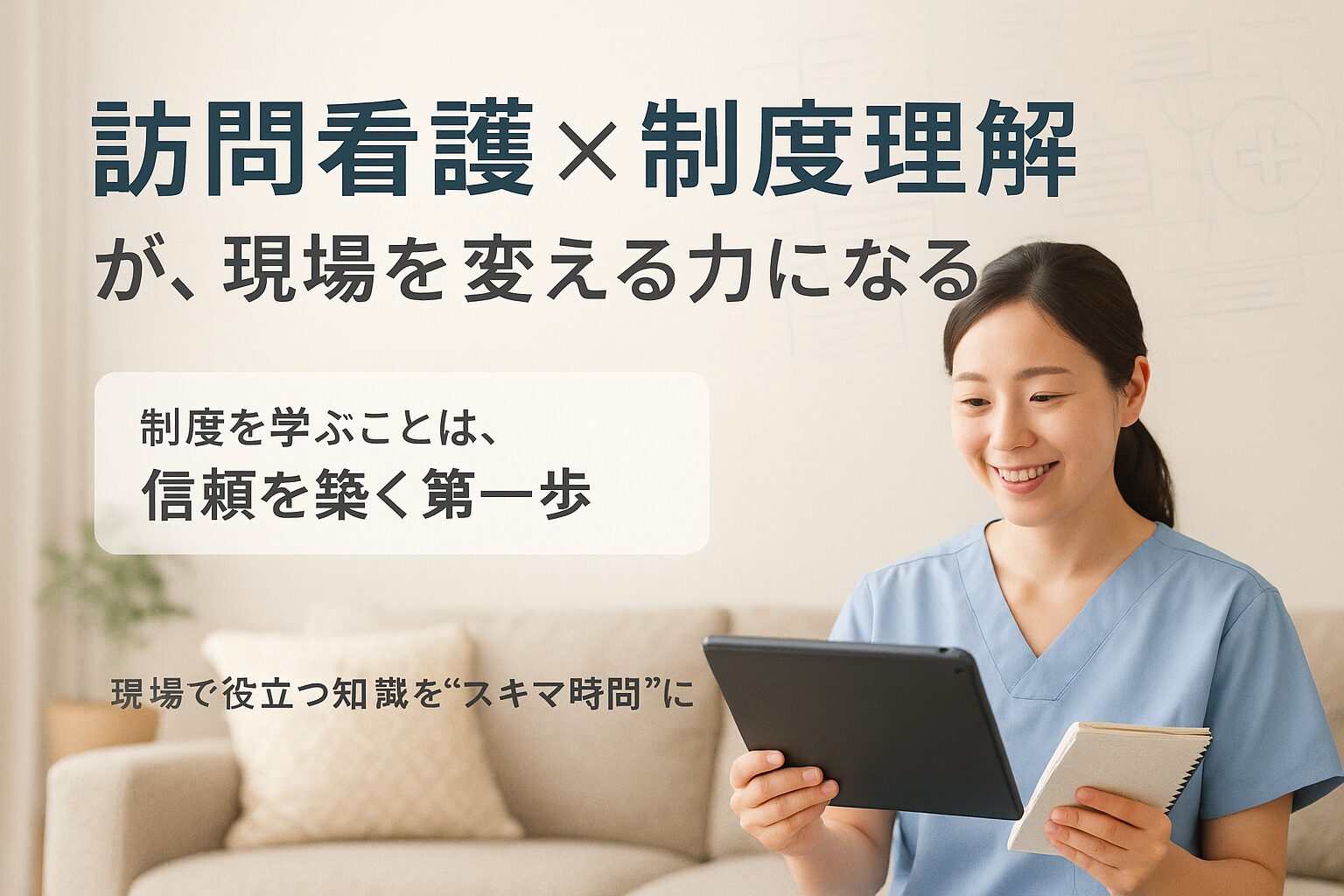看護師の皆さんのなかには、
- 訪問看護の仕事に興味があるけど制度が複雑そう…
- 現場では忙しくて制度のことまで手が回らない…
- 保険の仕組みは事務さんがやるから詳しくなくてもいいのでは?
という方もいるかもしれません。
ですが、実はこの「制度への理解」が、利用者様へのケアの質、そしてスタッフとしての信頼性を大きく左右するのです。
この記事では、制度を理解するメリットから、普段の業務でどう学んでいけばよいか、最後には役立つ学習ツールの紹介まで含めて、わかりやすくお伝えします。
訪問看護の現場では「制度」がすべてに関係している
訪問看護でのサービスは、主に医療保険と介護保険の枠組みの中で提供されます。
制度を知らずに働いていると、以下のような場面で困ることがあります。
- 利用者様の希望するサービスが制度上できない
- 主治医との連携で情報がかみ合わない
- ケアマネや他職種と話すときに理解が不十分で不安になる
たとえば、**「1週間に何回訪問できるか」**というのも、医療保険と介護保険で全く違いますし、利用者の負担割合や限度額、ターミナル期や精神疾患に関する扱いなども制度に基づいて決まっています。
スタッフがある程度制度を理解していれば、ケアプラン作成の際に建設的な提案ができたり、ご家族への説明にも安心感を与えたりすることができます。
制度を理解している看護師・療法士が現場で信頼される理由
1. 利用者様への説明に自信が持てる
ご家族やご本人から「このサービス、あと何回受けられるの?」「介護保険の点数って?」と質問されることはよくあります。
このときにすぐ答えられると、「しっかりした人だな」と信頼につながります。
2. 他職種との連携がスムーズになる
ケアマネや医師、福祉用具業者などとやりとりする際に、制度の共通言語が使えると話が早くなります。
理解がある人ほど、「この人と仕事したい」と思ってもらえる傾向があります。
3. サービスの提案力が上がる
例えば「医療保険から介護保険に切り替えるタイミング」や「訪問リハビリを併用する方法」など、選択肢が広がり、より柔軟にサービスが組み立てられるようになります。
4. 自分の業務の「限界と可能性」がわかる
制度のルールを知ることで、「ここまではできる」「これは制度的に難しいから別の手段を提案しよう」と判断が明確になり、不要なストレスが減ります。

知識は一気にではなく「業務の中」で育てる
制度は確かに複雑です。
一度に全部を覚える必要はありません。
大事なのは、**「その都度調べる・聞く・メモを取る」**の積み重ね。
よくある場面で学べるポイント
- ケアマネとの会話 → 要介護度・介護保険サービスの範囲
- 医師の指示書を見る → 医療保険の訪問頻度・疾患名の扱い
- レセプト確認 → 記録の書き方、算定要件の学び直し
- 退院前カンファ → 入退院時加算や早期訪問などの条件
訪問看護は自律的に考えて動くことが求められる仕事です。
だからこそ、制度を知っておくと「どう動けばいいか」の判断力が身につきます。
看護師・療法士が制度を学ぶのにおすすめのツール
制度のことを勉強したい、でも本や厚労省の資料は難しすぎる…。
そんな方におすすめしたいのが、動画で学べる「リハノメ」です。
リハノメとは?
理学療法士・作業療法士向けのオンライン学習プラットフォームですが、看護師さんにも役立つ内容がたくさん!
- 医療・介護保険制度の解説講座
- 訪問看護での記録・報告書の書き方
- チーム連携、倫理的配慮、コミュニケーション法
など、訪問看護ステーションで即使える知識が動画で学べます。
スマホでも視聴可能なので、スキマ時間にコツコツ続けやすいのも嬉しいポイントです。
最後に:制度を知ることは、利用者さまへの「安心」を届けること
訪問看護は、単に医療行為を提供するだけの場ではありません。
制度という「土台」を理解しながら、利用者さまの価値観に寄り添う柔軟な支援ができる看護師・療法士こそ、今後ますます求められる存在になります。
ぜひ、日々の業務の中で「なぜこうなっているんだろう?」と制度に目を向けてみてください。
そして、学びたいと思ったときは、無理せず楽しく学べるツールを活用しましょう。
今すぐ学び始めたい方へ
制度や訪問看護の知識を効率よく学びたいなら、こちらの「リハノメ」がおすすめです
PT.OT.STのための総合オンラインセミナー『リハノメ』忙しい中でも、少しずつ「自分の力」を高めていける環境を、あなた自身の手で整えていきましょう。
「知ってる」だけで現場は変わります。
これからも、制度を味方につけて、より良いケアを一緒に届けていきましょう。