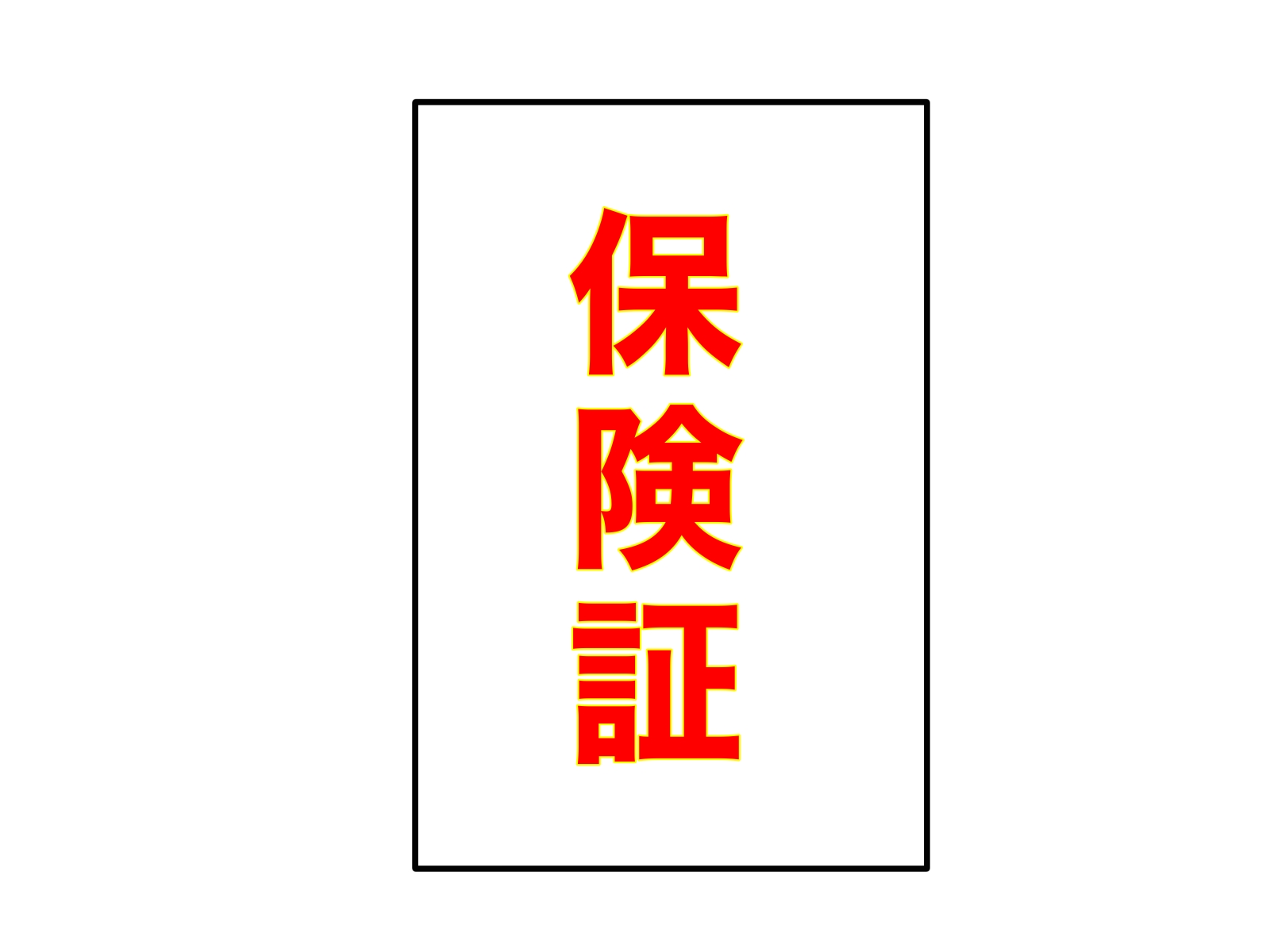日本の保険証の歴史
日本の保険証は、国民の健康を守るための医療保険制度に基づいて発展してきました。
その歴史を初心者にもわかりやすく解説します。
1. 保険証の起源:国民健康保険制度の創設
日本における医療保険制度の基盤は、1938年(昭和13年)の旧「国民健康保険法」の施行により築かれました。
- 初期の特徴:
- 保険者(運営主体)の設立や加入は任意であり、多くの国民が無保険状態でした。
- 当時、約3,000万人(国民の約3分の1)が医療保険に未加入だったとされています。
- 戦後の再建:
- 終戦直後はインフレーションなどで制度が危機に陥りましたが、その後、日本経済の復興とともに制度が強化されました。
- 1959年(昭和34年)には新しい「国民健康保険法」が施行され、市町村による運営が義務化されました。
2. 国民皆保険体制の実現
1961年(昭和36年)、日本は世界的にも珍しい「国民皆保険体制」を実現しました。
これにより、全ての国民が何らかの医療保険に加入する仕組みが整いました。
- 背景:
- 高度経済成長期を迎え、社会保障政策が充実。
- 医療費負担を軽減し、医療サービスへのアクセスを向上させることを目指しました。
- 主な改正点:
- 国庫負担率(政府からの補助金)を段階的に引き上げ、1966年には40%まで増加。
- 患者負担割合も引き下げられ、医療費自己負担が軽減されました。
3. 老人医療費無料化とその影響
1973年(昭和48年)、老人福祉法改正により、70歳以上の高齢者は医療費が無料となりました。
この制度は福祉政策として画期的でしたが、以下の影響も生じました。
- 利用者急増:
- 高齢者による医療サービス利用が増加し、「病院のサロン化」や「社会的入院」といった問題が発生。
- 財政への負担:
- 高齢化社会への突入とともに、医療費が急増し、財政運営が厳しくなりました。
4. 制度見直しと再編
1980年代以降、日本経済は安定成長期に入り、高齢化や財政問題への対応が求められました。
- 老人保健法(1983年施行):
- 高齢者にも一定額の自己負担を求める方式を導入。
- 新たな課題:
- 被用者保険(会社員向け)から退職後に国民健康保険へ移行する高齢者が増加し、高齢者加入率が上昇。
- 医療費増加による財政難への対応策として、段階的な患者負担引き上げや財政調整制度が整備されました。
5. 広域化と持続可能性への取り組み
近年では、医療保険制度を持続可能なものとするため、大規模な改革が行われています。
- 広域化(2018年施行):
- 国民健康保険は都道府県単位で財政運営されるようになり、小規模自治体での運営リスクを軽減。
- 後期高齢者医療制度(2008年導入):
- 高齢者専用の医療制度を設け、現役世代との費用負担区分を明確化しました。
6. 現在と未来
現在、日本では「国民皆保険体制」が維持されています。
しかし、高齢化や人口減少による課題も多く、新たな改革が求められています。
- 課題:
- 医療費削減や効率的な運営。
- 若い世代への負担軽減。
- 市民への協力要請:
- 保険料納付期限の遵守。
- 重複受診回避やジェネリック薬品使用推奨など1。
日本の保険証は、このような歴史と改革を経て進化してきました。現在も多くの人々に安心を提供する重要な社会基盤として機能しています。
Citations:
- https://www.city.kashiwa.lg.jp/hokennenkin/hokennenkin/kokuho/kohoshi/rekishi.html
- https://koazarashi.com/2020/01/25/post-6722/
- https://finance.yahoo.co.jp/brokers-hikaku/experts/questions/q12195487402
- https://www.med.or.jp/people/info/kaifo/history/
- https://manekomi.tmn-anshin.co.jp/hoken/17365369
- https://rakuya-k.co.jp/medical-insurance/history/
- https://www.dmcompany.co.jp/news/326
- https://www.hokenmarket.net/carna/life/post133.html