訪問看護ステーションと訪問リハビリテーションは在宅医療・介護の重要なサービスですが、その違いを法律・制度・基準・サービス内容の4軸で整理します。
両者の核心的な違いは「医療ケアの有無」と「専門職の役割分担」にあります。
1. 法律上の位置付け
訪問看護ステーション
- 根拠法:介護保険法(第8条第2項第3号)と医療保険法(健康保険法第63条)
- 指定条件:都道府県知事による「指定居宅サービス事業者」の認定が必要
- 法的定義:疾病や負傷により居宅療養が必要な者への看護師等による「療養上の世話」と「診療の補助」
訪問リハビリテーション
- 根拠法:介護保険法(第8条第2項第4号)と医療保険法(診療報酬制度)
- 指定条件:病院/診療所/介護老人保健施設が実施主体
- 法的定義:要介護者の心身機能維持・回復を目的としたリハビリ専門職による訓練
2. 制度設計の違い
サービス提供者
| 項目 | 訪問看護 | 訪問リハビリ |
|---|---|---|
| 実施主体 | 訪問看護ステーション | 医療機関/介護老人保健施設 |
| 主担当職種 | 看護師(常勤必須) | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 |
| 医師の関与 | 連携医師の確保が義務 | 施設に常勤医師が在籍 |
利用条件
- 訪問看護:要介護1~5(介護保険)/医師の指示書(医療保険)
- 訪問リハビリ:要介護1~5(介護保険)/通院困難な状態(医療保険)
3. 基準の違い
人員配置基準
| 職種 | 訪問看護 | 訪問リハビリ |
|---|---|---|
| 医師 | 連携医師(非常勤可) | 専任常勤医師1名以上 |
| 看護師 | 2.5人以上(常勤) | – |
| リハビリ職 | 任意 | 適当数配置義務 |
| 管理者 | 看護師資格必須 | 医療機関管理者 |
運営基準の特徴
- 訪問看護:24時間対応体制、緊急時訪問可能、薬剤管理記録の義務
- 訪問リハビリ:6ヶ月ごとの計画見直し、福祉用具アドバイス義務
4. サービス内容の違い
実施可能な支援
| 項目 | 訪問看護 | 訪問リハビリ |
|---|---|---|
| 医療処置 | 注射・点滴・褥瘡処置 | × |
| 生活支援 | 入浴/排泄介助 | 動作訓練指導 |
| 機能訓練 | 基本的ADL訓練 | 専門的リハビリ |
| 相談対応 | 24時間健康相談 | 福祉用具アドバイス |
| 緊急対応 | 急変時の対応可能 | 医療機関へ連絡 |
時間・回数制限
| 保険種別 | 訪問看護 | 訪問リハビリ |
|---|---|---|
| 介護保険 | 1日3回/週6回(20分単位) | 1日3回/週6回(20分単位) |
| 医療保険 | 週3回(30-90分/回) | 週6回(退院3ヶ月内は週12回) |
5. 費用負担の違い
自己負担額(1割の場合)
| サービス | 単価 | 加算項目 |
|---|---|---|
| 訪問看護 | 293円/30分 | 夜間・休日加算 |
| 訪問リハビリ | 292円/20分 | 短期集中加算 |
6. 選択のポイント
訪問看護が適するケース
- 胃瘻管理や点滴が必要
- 24時間の健康監視が必要
- 認知症による行動障害がある
訪問リハビリが適するケース
- 歩行機能の回復を目指す
- 住宅改修のアドバイスが必要
- 嚥下機能の改善が必要
両サービスは下表のように相互補完的に運用可能です:
| 連携事例 | 訪問看護の役割 | 訪問リハビリの役割 |
|---|---|---|
| 脳卒中退院後 | 血圧管理・服薬指導 | 歩行訓練・ADL訓練 |
| 骨折術後 | 創部処置・疼痛管理 | 関節可動域訓練 |
| パーキンソン病 | 服薬調整・転倒予防 | 姿勢保持訓練 |
まとめ
実際の利用では、ケアマネジャーが中心となり「居宅サービス計画」を作成します。
2025年4月現在、混合型サービスを提供する事業所も増加しており、看護師とリハビリ職が協働で訪問する「チームアプローチ」が注目されています。
この違いを理解する際のポイントは、看護が「現在の状態維持」を、リハビリが「機能回復」を主眼としている点です。
法律上の位置付けからサービス内容まで、両者の特徴を正しく把握することで、利用者個々のニーズに沿った適切なサービス選択が可能になります。

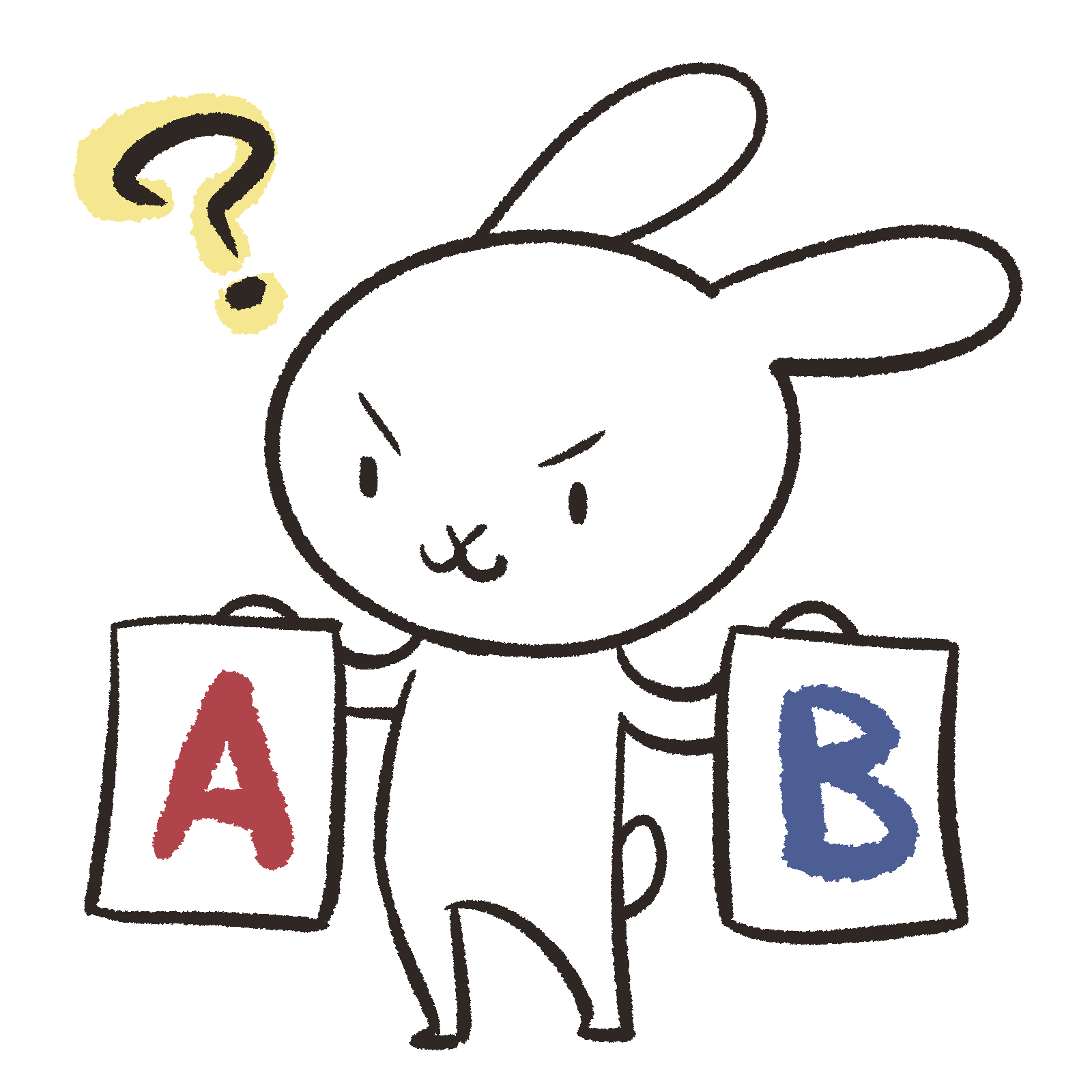
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/42f27818.ea190cf8.42f27819.1df4d901/?me_id=1213310&item_id=21346568&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0461%2F9784539730461_1_4.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/42f27818.ea190cf8.42f27819.1df4d901/?me_id=1213310&item_id=20643511&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2456%2F9784296112456_1_8.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

