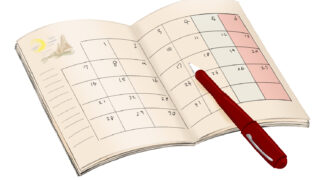 訪問看護
訪問看護 【紹介】訪問看護ステーションのスケジュールについて
訪問看護ステーションで働く看護師は、利用者の自宅や施設を訪問し、看護ケアを提供する仕事を行います。1日の訪問件数は平均5~6件程度で、移動時間や事務作業も含めたスケジュール管理が重要です。以下では、初心者にも理解しやすい具体例を交えて、典型的な1日の流れを詳しく解説します。
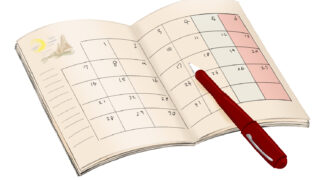 訪問看護
訪問看護  訪問看護
訪問看護  訪問看護
訪問看護  訪問看護
訪問看護 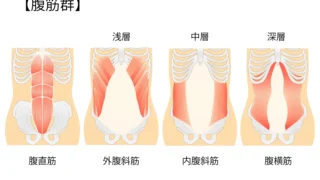 訪問看護
訪問看護  訪問看護
訪問看護 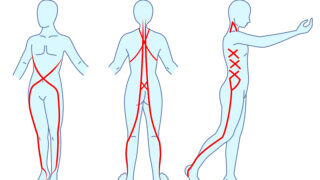 訪問看護
訪問看護  訪問看護
訪問看護  訪問看護
訪問看護 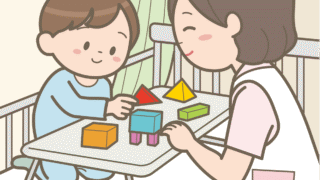 訪問看護
訪問看護