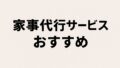- 理学療法士が訪問看護ステーションを立ち上げる際のメリットとデメリット
- 実際に開業を検討する際に押さえるべき視点
- 独立や事業展開を考える理学療法士の方にとっての判断材料
近年、医療機関や介護施設でキャリアを積んだ理学療法士が、「より自由度の高いリハビリ提供」や「地域包括ケアの一翼を担いたい」という想いから、訪問看護ステーションの立ち上げを検討するケースが増えています。
訪問リハビリは、病院のように診療報酬上の単位数や日数に厳しい制限がなく、利用者一人ひとりの生活に密着したリハビリを継続的に提供できる点で大きな魅力があります。特に、回復期を過ぎても改善意欲が高い方や、在宅生活を送りながら心身機能を維持したい方にとっては、欠かせないサービスとなり得ます。
一方で、訪問看護ステーションの運営には、人員基準や看護師の確保、保険制度による制約、営業活動の必要性など、多くのハードルが存在します。理学療法士が管理者にはなれないこと、また訪問リハはあくまで「訪問看護の一部」として位置づけられていることも、理解しておくべき重要なポイントです。
メリット
1) 病院のような算定上の制限に縛られにくい(生活期の継続性)
回復期病棟等では、2024年度改定で患者1日あたりの個別リハは原則「6単位(1単位20分)」が上限となりました(疾患・病棟条件で一部緩和あり)。
さらに医療保険のリハは疾患群ごとに標準算定日数が設定され、脳血管等180日、運動器150日、心大血管150日、廃用120日、呼吸器90日を超えると原則算定が難しくなります。
訪問看護に事業の軸足を置くと、病棟起点の「日内上限・入院期間」から解放され、生活期の継続支援(介護保険/医療保険/自費の設計を含む)を主戦場にできます。(厚生労働省)
補足:療法士側の“提供可能量”にも天井があり、通則では1人の療法士が実施できる標準は1日18単位(最大24単位)、週108単位とされます。病院内の工数制約から離れても、人員計画上はこの上限を念頭に置く必要があります。(PT-OT-ST.NET)
2) 生活環境で“個別のリハビリ”を設計できる
訪問看護では、医師の指示(訪問看護指示書等)に基づき、PT・OT・STが居宅での個別リハビリを提供できます。
住環境・福祉用具・家族介護力・地域資源に即した目標設定と介入が可能で、「病院でできる/できない」を超えた本質的なハビリテーションが実現しやすくなります。(厚生労働省)

デメリット(=起業時に直面する制度・経営上のハードル)
1) 介護保険の“時間上限”と“支給限度額”の壁
- PT・OT・STによる訪問看護(介護保険)の週上限
1人の利用者に対し、**20分以上×週6回まで(=実質120分まで)**が限度です。生活期での頻回訓練の希望があっても、介護保険枠だけで組むと時間制約にぶつかります。(厚生労働省) - 区分支給限度基準額(月額上限)
要介護度ごとに月の支給限度が定められ(例:要介護1で16,765単位≒約167,650円)、プランが限度を超えると超過分は自費になります。 - ケアマネと上限管理をしながら、看護・リハの優先順位づけと短期目標の再設計が不可欠です。(介護検索, 堺市公式ウェブサイト)
2) ケアプラン前提(介護保険)と医師指示前提(両保険)
- ケアプランはケアマネジャーが作成
介護保険サービスはケアマネ作成のケアプランに位置づくことで給付対象となるため、支援内容・頻度・組み合わせはケアマネとの合意形成が前提です。新規開業時ほど地域の居宅介護支援事業所/包括との連携力が成果を左右します。(厚生労働省) - 医師の指示・許可が大前提(医療/介護)
訪問看護は医師の指示に基づく保険サービスであり、PT等の関与もこれに基づいて行われます。主治医連携の導線設計(指示・情報共有・フィードバック)が必須です。(厚生労働省)
3) 医療保険では訪問回数に制約がある
医療保険の訪問看護は原則:1日1回・週3回まで。特別訪問看護指示書発行や別表該当疾患等で一時的に週4日以上が認められる枠はありますが、常時の高頻度は難しいため、医療×介護×自費のハイブリッド設計が現実解になります。(地方厚生局, 訪問看護のソフト(システム)・電子カルテはカイポケ訪問看護)
4) 看護師人員基準と管理者要件(“看護事業”としての骨格)
- 人員基準:看護職員(保健師・看護師・准看護師)を常勤換算2.5人以上配置が必要。実務上は欠勤・夜間体制も見込み、看護師3名以上の常時雇用が現実的ラインとなります。(PT-OT-ST.NET)
- 管理者要件:管理者は看護師(保健師・看護師)でなければならず、PTが管理者になることはできません。よって看護管理者の確保が最初の関門です。(Clinical Support)
- 人材市況:看護師は医療機関も含めて慢性的に不足。採用・教育・定着のため、シフト設計・夜間当番の負担分散・教育投資を初期から制度化しておく必要があります(自治体の人員基準案内等も参照)。(日本シグマックス整形外科領域 総合情報サイト SIGMAX MEDICAL)
5) 24時間体制・緊急時対応(負担と最近の緩和)
- 電話受付の一部をPT・OT・ST等でも可に(要件付き)
2024年度の介護報酬・診療報酬の見直しで、連絡相談窓口(緊急時の電話受付)を看護師以外の職員が担当できる道が開かれました。 - ただし医療的判断や緊急訪問の要否決定は看護師(または保健師)が必須、即時エスカレーション・記録・マニュアル整備・届出等が求められます。導入には体制整備・周知・同意取得が前提です。(厚生労働省)
- 実務的含意:24時間対応加算や緊急時訪問看護加算を算定する場合、オンコール負担は看護師に集中しがち。PTが一次受電に入れる体制を“あくまで電話窓口の一部”として取り入れると、夜間の初動負荷分散と看護判断の前段整理に寄与します。(厚生労働省)
6) 営業/関係構築が必要(紹介経路の多様化)
利用者の主な紹介元は地域包括支援センター(包括)・居宅介護支援事業所(ケアマネ事業所)・医療機関です。
病棟のように“内向き”の紹介動線はなく、説明会・同行訪問・退院前カンファ・フィードバックレター等を通じて地域連携の信用残高を積み上げる営業活動が欠かせません。

制度を踏まえた“勝ち筋”の設計ポイント
- プロダクト設計(誰に・何を・どう届けるか)
- 看護体制のデザイン
- 看護師3名以上を“常時運用できる”体制で採用。夜間・休日オンコールは**ローテーション+一次受電(PT/OT/ST)**の“プロトコル運用”で負担を平準化。(PT-OT-ST.NET, 厚生労働省)
- 医師・ケアマネ連携の型化
- 指示書→情報提供書→到達度レターの往復テンプレートを整備。ケアプラン原案への提案文(頻度・目標・卒業条件)を定型化して、説明責任と合意形成を高速化。(厚生労働省)
- 退院前から入る地域連携
- 退院支援カンファに標準で参加し、在宅初月の看護×リハ複合導線を敷く。緊急時加算を漫然と狙うのではなく、夜間コールの適正化・家族教育で質と効率を両立。(厚生労働省)
- KPIと単価管理
- 区分支給限度額の範囲で優先課題に資源集中。**到達指標(転倒・再入院・A(ADL)/IADL・参加)**をモニターし、週回数・時間の根拠をケアマネ会議で説明可能に。(介護検索)
立ち上げ前チェックリスト(抜粋)
- 管理者(看護師)を確保し、**看護職2.5人以上(常勤換算)**の採用計画・教育計画を作成。(PT-OT-ST.NET, Clinical Support)
- 24時間連絡体制の運用設計:受電マニュアル、PT/OT/STの一次受電可否・訓練、即時エスカレーション、同意取得、届出。(厚生労働省)
- 主治医連携:指示書の流れ、特別指示書の緊急時運用(14日間・週4日以上等の例外)を理解し院内説明資料を用意。(地方厚生局)
- ケアマネ連携:ケアプラン位置づけ前提の説明ツール(頻度・目標・卒業条件・優先順位)をテンプレ化。(厚生労働省)
- 限度額管理:区分支給限度基準額の早見表と、医療×介護×自費の切替アルゴリズムを整備。(介護検索, 堺市公式ウェブサイト)
- 人材採用ブランディング:夜間負担の見える化、エスカレーション設計、教育×評価×報酬の連動。

まとめ
PTが訪問看護ステーションを率いる最大の価値は、「生活期の“個別性”を主役に据えたリハビリテーション」を地域に根づかせられることです。
一方で、看護人員基準・24時間体制・保険ごとの時間/回数上限・ケアプラン前提・医師指示前提という看護事業としての要件は、起業初期の成否を左右します。
制度の“上限”を前提に、短期集中的に成果を出す設計、看護体制の負担分散、医師・ケアマネとの合意形成、そして地域連携という営業を組み合わせることで、利用者・家族・紹介元から選ばれる“強い訪問看護”を実現できます。
参考(本文で言及した主な一次情報)
- 回復期等の個別リハ上限(1日6単位 2024改定)(厚生労働省)
- 疾患群別・医療リハの標準算定日数(例:心大血管150日等)(厚生労働省)
- 療法士の1日/週の実施上限(18/24単位、週108単位)(PT-OT-ST.NET)
- 介護保険下のPT/OT/STによる訪問看護は20分×週6回(=120分)まで(厚生労働省)
- 区分支給限度基準額(要介護度ごとの月上限)(介護検索, 堺市公式ウェブサイト)
- ケアプランはケアマネが作成(位置づけの根拠)(厚生労働省)
- 医療保険の訪問看護回数(原則週3日、特別指示書等で例外)(地方厚生局, 訪問看護のソフト(システム)・電子カルテはカイポケ訪問看護)
- 訪問看護の概要(医師指示の前提)(厚生労働省)
- 看護職2.5人以上(常勤換算)/管理者は看護師の要件(PT-OT-ST.NET, Clinical Support)
- 24時間連絡体制の電話受付における非看護職関与の緩和(要件付き)(厚生労働省)